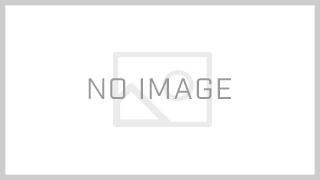心原性心停止で、偶発的低体温になった患者で予後が良かったり、心原性心停止の犬で軽度低体温療法が脳障害を減少させたという報告があった。人を対象とし軽度低体温療法の有効性を検証したRCTは、2002年に初めて報告された (HACA試験)。(1)。
心室細動 (VF) による院外心停止を対象とし、32−34℃・24時間の体温管理を行う群と、体温管理を行わない群に無作為化。体温管理にはTheraKoolという冷気が出るマットレスを使用。目標体温に到達するまでの時間は8時間 (中央値) で、復温は受動的に行い、36℃以上になるのに8時間 (中央値) かかっている。標準治療群では、体温は37℃台で推移。
登録が進まず、かつ資金が不足したことにより早期中止になっているが、273例が登録され、6ヶ月死亡率は低体温療法群で41%、通常治療群で55%であった (リスク比:0.74、95%CI:0.58−0.95)。
さらに小規模のRCTではあるが、VFによる心停止を対象とし、32−34℃・12時間の低体温療法と通常体温と比較。低体温療法群で神経学的予後が有意に改善することが示された (49% vs 26%)(2)。
この2つのRCTの結果を受け、VFによる院外心停止で体温管理療法 (TTM) が標準治療としてガイドラインで推奨されるようになった。
ただ、TTMの脳保護効果について、遅発性細胞死の抑制、脳代謝抑制、フリーラジカル産生抑制などによるものと推測されているが、そのメカニズムはよくわかっていない。実は、低体温にすることに生命予後や神経学的予後を改善させる効果はないのかもしれない。
ある観察研究では、ROSC後48時間以内に体温が37℃から1℃上昇するごとに、神経学的予後が悪化することが示されている (オッズ比:2.26)(3)。生命予後や神経学的予後の改善が示された上の2つのRCTでも、通常体温群の体温 (中央値) は37℃台になっていたことから、低体温がアウトカムの改善をもたらしたのか、あるいは37℃を超える体温が予後の悪化をもたらしたのかはわからない。
32−34℃の低体温が生命予後や神経学的予後を改善したのではなく、高体温を避けることがそれらのアウトカムの改善につながったことを示唆したのが、TTM試験である(4)。
993例の院外心停止を、目標体温33℃と36℃に無作為化し、72時間は両群とも発熱を避けるという方法が取られた。primary endpointは試験終了 (中央値256日) までの全死亡、secondary endpointは180日時点の神経学的予後不良と死亡とし、いずれも両群に有意差はなく同程度だった。
全有害事象は33℃群で多い傾向で、低K血症は有意に、肺炎や穿刺部出血などは多い傾向が見られた。
この結果から、36℃の体温管理を行うことは妥当と考えられるが、すべての患者で33℃が無益かどうかについては明らかではなく、例えば、より重症な患者 (体動がない・脳幹反射消失・頭部CTですでに虚血性変化を認めるなど) では、33℃を目標としたTTMが良いかもしれない。
TTMの目標体温は少なくとも24時間維持することが推奨されているが、24時間と48時間を比較したRCTでは、両群で神経学的予後に差はなく、48時間で有害事象が有意に多かった (そのメインは肺炎)(5)。このRCTは目標体温を33℃としており、低体温による細胞性免疫の低下や筋弛緩薬投与による喀痰排出不全が原因と推測する。
まとめると、VFによる院外心停止には目標体温32−36℃とし24時間以上のTTMが推奨されているが、基本的には35−36℃程度での体温管理を行い (それ以上下げようとすると多くの場合で筋弛緩薬が必要になる)、72時間以内の発熱は避けるというスタンスで良いだろうと思います。
(1) N Engl J Med. 2002;346:549–56.
(2) N Engl J Med. 2002;346:557–63.
(3) Arch Intern Med. 2001;161(16):2007-12.
(4) N Engl J Med. 2013;369(23):2197-206.
(5) JAMA. 2017;318(4):341-350.