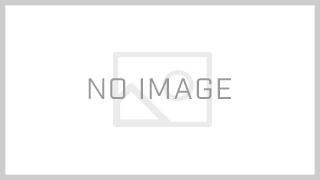Impact of new development of ulcer-like projection on clinical outcomes in patients with type B aortic dissection with closed and thrombosed false lumen.
Circulation. 2010 Sep 14;122(11 Suppl):S74-80
背景
この研究の目的は、intramural hematomaとして知られる偽腔閉塞型急性大動脈解離stanfordBにおいて、新規のulcer-like projection(ULP)の臨床的重要性を検証することである。
方法/結果
1986−2008年の間に神戸市立医療センターに入院し薬物療法が行われた、偽腔閉塞型急性大動脈解離stanfordB170例が対象である。慢性期の死亡が31例で、うち9例が大動脈破裂により死亡した。全患者の1年生存率は99%、5年生存率は89%、10年生存率は83%であった。62例(36%)で発症30日いないに新規のULPを認めた。ULPは有意に生存率を悪化させ、adverse aorta-related eventsと関連する。さらに、近位部下行大動脈にULPがある場合、それ以外に部位と比較し有意にadverse aorta-related eventsが増加する。初期の大動脈径(HR:3.55)と近位部下行大動脈のULP(HR:3.79)は、adverse aorta-related eventsの強い予測因子であった。
結論
偽腔閉塞型急性大動脈解離stanfordBにおいて、初期の大動脈径と近位部下行大動脈のULPは、いずれもadverse aorta-related eventsの強い予測因子であった。ULPが新規に出現した患者は、ULPがない患者よりも慎重なフォローアップと画像検査を行うべきである。
◯論文のPICOはなにか
P:発症48時間以内の偽腔閉塞型急性大動脈解離stanfordB
I/C:ULPの有無
O:adverse aorta-related events(大動脈破裂、偽腔開存型大動脈解離、60mm以上の大動脈拡大、外科的手術)
◯結果
デザイン:後向きコホート研究
登録期間:1986−2008年
フォローアップ期間:平均7.1±4.9年
outcome観察者のmasking:なし?
交絡因子の調整:Cox比例ハザードモデル(変数:年れ、性別、高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙、最大大動脈径、偽腔最大径、ULPの存在、近位部下行大動脈のULP)
最大大動脈径と近位部下行大動脈のULPが、adverse aorta-related eventsの強力な予後因子であった。
最大大動脈径(39±5mm vs 34±5mm、HR:3.55、95%CI:1.79−7.04)
近位部下行大動脈のULP(HR:3.79、95%CI:1.57−9.17)
ULP(+)はULP(-)と比較し実際の死亡率が有意に高いが、交絡因子の調整はされていない。
◯感想/批判的吟味
分枝閉塞や灌流障害を来したような急性大動脈解離(AD)であれば、stanford Bでも手術適応ということになるが、周術期死亡率は高い。そのような症例にはステントグラフトによる治療が考慮される。uncomplicated ADに対してどこまで適応されうるかは議論があるところ。ただ、この研究にあるように近位部下行大動脈にULPを有する症例や大動脈が拡大した症例では、ステントグラフトを考慮してもいいかもしれない。